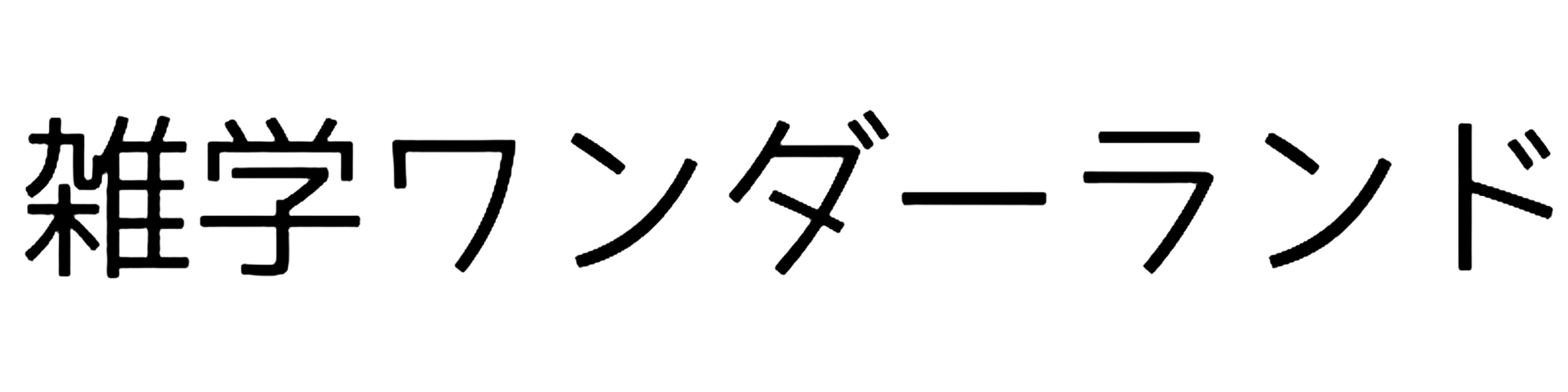チエコさん
チエコさん日本でオリンピックを五輪と呼ぶのは、オリンピックシンボルの5つの輪から来ているのでしょうか。



実は「五輪」には、深くて意外な由来があります。今日はその話をしましょう。
オリンピックと「五輪」の関連


「五輪」は日本の武道や剣道において使用される用語であり、オリンピックは世界中の競技スポーツに関連した国際的なスポーツイベントです。両者は異なる文脈と目的を持っていますが、一般的には混同されているようです。
「五輪」とはオリンピックの別名か?
「五輪」と「オリンピック」は、一般的には関連がある言葉ですが、厳密に言えば「五輪」は「オリンピック」の別名ではありません。以下にそれぞれの語の関連と違いを説明します。
オリンピック(Olympics)
オリンピックは、国際的なスポーツ大会の総称で、夏季オリンピックと冬季オリンピックの2つの主要な形式があります。これらの大会は、世界中からアスリートが集まり、さまざまな競技で競い合うイベントです。オリンピックは、国際オリンピック委員会(IOC)によって統括されており、特定の年に特定の都市で開催されます。
五輪(Gorin)
「五輪」は、日本の文化や武道に関連する言葉で、主に「五輪の書」という宮本武蔵の著作に関連しています。宮本武蔵の「五輪の書」は、剣術と武道の技術、哲学、修行についての指南書です。この文脈では「五輪」は武道や剣術における概念であり、オリンピックとは直接の関連はありません。
オリンピックの歴史と「五輪」の使われ方
ここではオリンピックの歴史と「五輪」の使われ方について、わかりやすく説明します。
オリンピックの歴史
オリンピックは、古代ギリシャ時代に遡る歴史的なスポーツイベントです。最初のオリンピックは紀元前776年に古代オリンピアで開催されました。これらのギリシャの祭典は、異なる都市国家のアスリートが競技大会で競い合い、神々への敬意を表す機会でした。古代オリンピックは、紀元前4世紀から紀元後4世紀まで続き、古代ギリシャ文化の一部として重要な存在でしたが、後に中断しました。
近代オリンピックの誕生
近代オリンピックは、フランスのバロンピエール・ド・クーベルタンによって提唱され、1896年にアテネで復活しました。これを契機に、近代オリンピックは国際的なスポーツ大会として定着し、夏季オリンピックと冬季オリンピックの2つの主要な形式が発展しました。
「五輪」の使われ方
日本の「五輪」は、主に宮本武蔵の著作「五輪の書」に関連して使われます。この書は、宮本武蔵の剣術や武道の哲学、技術についての指南書で、剣道や武道の修行者に向けて書かれました。「五輪」は、武蔵の剣術スタイルである「二天一流」の中で重要な要素であり、無剣取りや実戦的な技術を含んでいます。この文脈では「五輪」は武道の概念として使用され、オリンピックとは直接の関係はありません。
「五輪の書」とは何か?
「宮本武蔵肖像」引用:Wikipedia
ここでは宮本武蔵の人物像と「五輪の書」について、分かりやすく説明します。
宮本武蔵の人物像
宮本武蔵は、1584年に生まれました。出生地については、兵庫県と岡山県の2つの説があります。彼は若い頃から剣術に優れ、多くの戦いで名声を高めました。
彼の最も有名な業績は、1612年に行われた「巌流島の戦い」で、敵対する剣士の佐々木小次郎との壮絶な一騎討ちでした。この戦いで宮本武蔵は勝利し、その剣技と戦術により日本中で評判となりました。
宮本武蔵はまた、剣道の創始者としても知られており、その剣術の理念は「無剣取り」や「一刀両断」など、非常に合理的で効果的な技術を追求しました。
彼は晩年、隠居して書道や禅の修行に専念し、著作も多く残しました。彼の代表作である「五輪書」は、武道の指針として今日でも尊重されています。
宮本武蔵は日本の剣道や武道の伝説的な存在であり、その剣術のスキル、哲学、そして人生への姿勢は、多くの人に尊敬されています。
「五輪の書」の内容と目的の説明
宮本武蔵が著した「五輪の書」は、日本の武道の古典として尊重され、多くの武道家や剣道家に影響を与えています。
その内容は、剣術の実践だけでなく、精神的な成長と倫理的な価値観についても考えさせるものとなっています。
剣術の指南書
「五輪の書」は、宮本武蔵が自身の剣術の経験と哲学をまとめた指南書です。彼の剣術スタイルである「二天一流」に関する技術や戦術、修行方法などが詳細に記述されています。
実戦的なアプローチ
宮本武蔵の剣術は、実戦において有効な技術を追求するものであり、冗長な動きや無駄を排除することを重視しています。「五輪の書」は、実戦的な戦闘技術を教えることを主要な目的としています。
無剣取りの哲学
この著作は、無剣取りと呼ばれる剣を抜かずに相手を制する哲学に基づいています。剣を持たずに相手の攻撃を防ぐ技術や心の集中力を強調し、戦闘において相手を制するための方法論を提供しています。
精神的な側面
「五輪の書」は、剣術の技術だけでなく、精神的な側面にも焦点を当てています。武蔵は、修行と剣術の結びつきを強調し、内面の成長と鍛錬を通じて武道の真髄に到達することを教えています。
宮本武蔵とオリンピックの結びつき


宮本武蔵の哲学とオリンピックの理念は、努力、品格、精神的な価値、国際的な協力と友情に焦点を当てており、競技としてのスポーツや武道における共通の価値観を反映しています。
宮本武蔵の哲学とオリンピックの理念の共通点
宮本武蔵の哲学とオリンピックの理念にはいくつか共通点があります。以下に、それらの共通点をわかりやすく説明します。
努力と成長の追求
宮本武蔵は剣道や武道の修行を通じて、自己超越と成長を追求しました。彼の哲学は、日々の努力と継続的な修行を通じて技術と内面の成長を達成することを強調しています。
一方、オリンピックの理念には、アスリートが最高のパフォーマンスを目指し、過去の自分を超えることが含まれています。オリンピックは競技者が努力し、成長し続ける場であり、その過程で個人や国際的な友情と協力を促進します。
品位と精神的な価値
宮本武蔵は武道の中で品格と礼儀正しさを尊重しました。彼の哲学は、剣道の技術を駆使しながらも、相手に対する敬意と誠実さを忘れないことを教えています。
そして、オリンピックの精神は競技者の品格とフェアプレーを重要視しています。アスリートは競技の中で競い合いつつも、相手を尊重し、公正で礼儀正しい態度を示すことが求められます。
国際的な協力と友情
宮本武蔵は日本の武道を代表し、その圧倒的な剣術の実力は海外においても大変な人気を誇ります。彼は異なる剣術スタイルや文化と交流し、その中で学びました。
それと同様に、オリンピックは異なる国々からのアスリートが一堂に会する国際的なイベントであり、国際協力と友情を奨励します。オリンピックは文化交流と国際的な理解を促進する役割を果たしています。
「五輪の書」がオリンピックに与えた影響
宮本武蔵の「五輪の書」がオリンピックに直接的な影響を与えたわけではありませんが、間接的な影響を通じていくつかの重要な価値観や哲学的な要素がオリンピック運動に影響を与えた可能性があります。その間接的な影響を示すいくつかの要点を説明します。
精神的な価値観
宮本武蔵の「五輪の書」には、剣道や武道の修行を通じて内面の成長や精神的な価値観の重要性が強調されています。
オリンピック選手や競技者も、精神的な強さや道徳的な価値観を尊重し、スポーツにおけるフェアプレーを奨励しています。
努力と成長
宮本武蔵は努力と継続的な修行を重要視し、自己超越を追求しました。オリンピックの精神も、アスリートが努力と成長を通じて最高のパフォーマンスを目指すことを強調しています。アスリートの努力と成長がオリンピック活動の中心的な価値です。
フェアプレーと協力
宮本武蔵の剣道における礼儀正しい態度や相手への敬意は、競技の中でのフェアプレーと協力に通じています。オリンピックにおいてもフェアプレーを重要視し、アスリート同士の競争が公正で礼儀正しいものであることを促進します。
また、オリンピックは異なる国々からのアスリートが一堂に会し、国際的な協力と友情を醸成する場でもあります。
人間の潜在能力
宮本武蔵の「五輪の書」は、人間の潜在能力を最大限に引き出すことを追求しています。
オリンピックも同様にアスリートが自身の限界に挑戦し、最高のパフォーマンスを発揮する場として、
人間の潜在能力を信じる価値観を体現しています。
「五輪」がオリンピックに定着した瞬間


日本においてオリンピックが「五輪」と表現されるようになった背景には、一人のジャーナリストの奮闘努力がありました。
「五輪」の呼称を定着させた歴史的な出来事
「五輪」(ごりん)という表現がオリンピックに関連して使われるようになったエピソードについて、川本信正さんの貢献を通じて説明します。
川本信正さんは、朝日新聞の運動部記者として活動していた日本のジャーナリストで、1924年のパリオリンピックを取材するためにフランスに派遣されました。彼が「五輪」という表現を使ったのは、日本語でのオリンピックの表現を新しく創り出そうとした考え抜いた結果です。
当時、オリンピックの日本語表現は「オリンピック競技大会」という長いもので、一般の人々にとって口にしにくいものでした。川本信正さんは、より簡潔で覚えやすい言葉を模索し、日本文化や武道の「五輪」のイメージを取り入れるアイデアを思いつきました。
この新しい表現を使って、川本信正さんは朝日新聞の記事において、パリオリンピックを「五輪」と表現しました。
この言葉は親しみやすく、簡潔な言葉であり、一般の読者にも受け入れられました。その後、「五輪」という表現は日本国内外で一般的に使用され、オリンピックの日本語表現として定着しました。
川本信正さんの「五輪」という表現の提案は、オリンピックに関する日本語表現を大幅に改善し、広く受け入れられるようになった重要な歴史的出来事であり、彼の貢献は今日まで続いているといっても過言ではありません。
なお、オリンピックシンボルの5つの輪には「5つの大陸」という意味がありますが、それ以外にも5つの自然現象である「水の青・砂の黄色・土の黒・木の緑・火の赤」を示しているという説があります。この説と合わせると、川本さんが「五輪」という言葉を選んだ理由もより理解しやすくなるかもしれません。
「五輪の書」が伝える価値観


宮本武蔵の哲学は、剣道や武道に焦点を当てながらも、その価値観や教訓はより広く私たちの生活に応用できます。
宮本武蔵の哲学から学ぶこと
宮本武蔵の哲学から、現代に生きる私たちが学ぶことができる重要な教訓や価値観は以下の通りです。
努力と継続の重要性
宮本武蔵は、剣道や武道の修行を通じて、努力と継続の大切さを強調しました。現代においても、どんな目標や夢に向かっても、努力と忍耐が成功への道を切り開きます。困難に立ち向かい、継続的に努力することが重要です。
自己超越
宮本武蔵の哲学は、自己超越と成長を重視しています。彼の教えから学ぶことは、自己啓発や個人の潜在能力を最大限に引き出すことの価値を理解することです。現代の社会では、自身のスキルや知識を向上させ、成長を促進する重要性が高まっています。
フェアプレーと協力
宮本武蔵は礼儀正しさや相手への敬意を尊重しました。この価値観は、現代の社会においても重要で、他人と協力し、
フェアな競争を大切にすることが成功と人間関係の鍵です。フェアプレーの原則はスポーツだけでなく、ビジネスや人間関係にも適用できます。
品格と倫理
宮本武蔵は剣道を通じて品格と道徳的な価値観を教えました。倫理的な行動や正しい判断は、現代社会でのリーダーシップや個人的な発展において不可欠です。彼の哲学から学ぶことは、正直さ、誠実さ、そして他人への思いやりを育てることです。
現在に生きる
宮本武蔵は「五輪の書」の中で「今ここに生きる」という考えを強調しました。過去や未来にとらわれず、現在に集中し、現実を受け入れることの重要性を訴えました。この教えは、マインドフルネスやストレス管理に役立つものとして、現代社会に適用できます。
まとめ:オリンピックと「五輪の書」の関連性


オリンピックと宮本武蔵の「五輪の書」は異なる文脈で生まれたものですが、共通点も存在します。
両者は共に努力と成長、品格、フェアプレー、精神的な価値観、国際的な協力と友情の重要性を強調しています。オリンピックは国際的なスポーツ大会であり、アスリートが最高のパフォーマンスを目指す場で、宮本武蔵の哲学と同様に努力と自己超越が重要視されます。
両者は異なる文脈で存在しますが、スポーツと武道を通じて個人と社会の成長を促進し、共通の価値観を提供する点において、非常に似通っていると言っても良いでしょう。



宮本武蔵の高潔な精神は、スポーツが持っている価値観にも当てはまりますね。



海外の多くの皆さんが「五輪の書」や「武士道」に興味を持ってくださるのもよく理解できます。