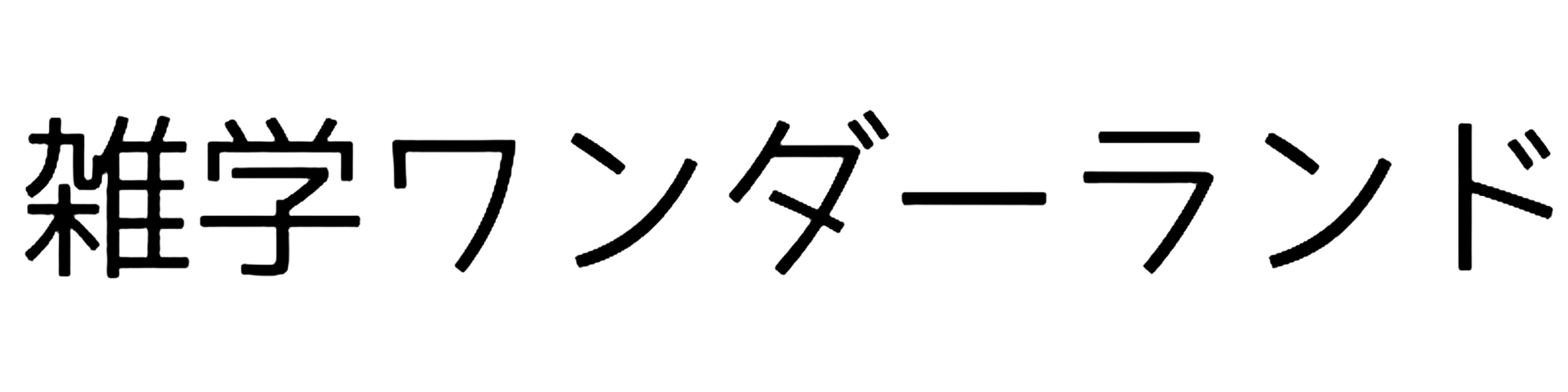チエコさん
チエコさん日本には古くから、たくさんの「しきたり」がありますね。



この記事ではそのうちのいくつかを紹介します。「しきたり」の面白さを一緒に学びましょう。
還暦に「赤いちゃんちゃんこ」を着る理由は?


還暦とはどのような節目なのか、また赤いちゃんちゃんこにはどういった意味があるのかを調べてみました。
還暦とは?
還暦は、60歳を迎えた節目の年を意味します。干支の巡り合わせに基づく暦法において、60歳を迎えると、生まれた年の干支に戻ります。新たな干支を迎えるということは、新たな人生の始まりを意味します。
還暦に赤いちゃんちゃんこを着る理由
還暦に赤いちゃんちゃんこを着る理由は、主に以下の2つが考えられます。
赤い色の持つ縁起の良さ
赤い色は、古くから邪気を払い、災いを避ける力があると信じられてきました。そのため、還暦を迎えた人が赤いちゃんちゃんこを着るのは、新たな人生の始まりを祝うとともに、これからの人生を健やかに過ごしてもらいたいという願いが込められています。
赤ちゃんに戻るという考え方
還暦は、人生の折り返し地点であり、同時に新たな門出でもあります。古来より、60歳はひとつの区切りとして捉えられており、還暦を迎えた人は生まれ変わった赤子のように無垢な存在とみなされてきました。赤いちゃんちゃんこを着る習慣は、こうした還暦の意味合いを反映したものと考えられています。赤は生命力や魔除けの色とされ、赤ちゃんに着せる産着にもよく用いられます。還暦を迎えた人が赤いちゃんちゃんこを身につけることで、生命力にあふれ、新たな人生を力強く歩んでいくことを願う気持ちを表しているのです。
また61歳は男女ともに厄年とされるため、赤いちゃんちゃんこには厄除けの意味合いもあるとされています。厄払いをすることで、これからの人生を健やかに過ごしていきたいという願いが込められています。
このように、赤いちゃんちゃんこは、還暦を迎えた人への祝福と、新たな人生への希望を象徴するものです。
赤いちゃんちゃんこの歴史
赤いちゃんちゃんこを着る習慣が始まったのは、江戸時代のことだと考えられています。当時はちゃんちゃんこを着て、寺社に参拝することが一般的に行われていました。
明治時代
明治時代になると、赤いちゃんちゃんこは、還暦を迎えた人への祝い着として、人々の間で広く親しまれるようになります。赤いちゃんちゃんこを着て、家族や親せきが集まり、還暦を迎えた人を祝う「還暦祝い」の習慣も定着しました。
大正時代
大正時代になると、赤いちゃんちゃんこは、還暦祝いの象徴として広く認知されるようになりました。還暦を迎えた人を祝福する気持ちを表すために、様々な色や意匠を凝らした赤いちゃんちゃんこが作られるようになりました。
昭和時代
昭和時代になると、赤いちゃんちゃんこは、還暦祝いの象徴として、人々の生活に深く根付いていきます。赤いちゃんちゃんこを着て、家族や親戚と記念写真を撮影する習慣も生まれ、還暦祝いの大切な思い出として残るようになりました。
還暦祝いの赤いちゃんちゃんこを着る際の注意点
赤いちゃんちゃんこは、羽織るように着るのが一般的です。頭巾付きのものも多く、一緒に着用することで、より華やかさを演出できます。
「トイレの神様」の話


日本では昔から、トイレをきれいにしておくと健やかな赤ちゃんが生まれるという言い伝えがあります。
トイレの神様の正体
トイレの神様とは、烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)という神のことです。この烏枢沙摩明王は、炎の力で汚れを清めて浄化してくれます。心だけでなく、日常生活のあらゆる不浄も焼き尽くし、清めてくれると信じられています。トイレに花を飾る習慣も、烏枢沙摩明王を祀るところから始まったと言われています。昔は便所に神棚を設け、花や酒を供えていたということです。
トイレをきれいにしておくと美しい子が生まれる理由
トイレの神様は女性の守り神で、お産とも深くかかわっていると考えられています。中国にも美しい厠の女神の伝説があり、その伝説が日本に伝わった可能性もあります。トイレの神様の信仰では、母胎にいる赤ちゃんを男の子にする力がある信じられたので、男子を求める戦国時代には広い地域に伝わりました。
こうしたことから、妊婦さんがトイレをきれいに掃除すると女性に願いが成就し、美しい子が生まれると言われるようになりました。地域によっては、臨月になるとトイレで安産祈願をしたり、出産後はトイレ参りをして健康を祈願する場合もあります。
お葬式でもらう「清めの塩」の意味と使い方


葬儀に参列者には、小さな紙の袋に入った塩を手渡されることがあります。この「清めの塩」の由来と適切な使い方について考えましょう。
清めの塩の意味とは
古くから受け継がれてきた知恵、清めの塩には、目に見えない力によって、家や体を清め、心を落ち着かせる効果があります。死は避けられない自然の摂理であり、人の死には邪気が寄り付くと考えられてきました。
清めの塩は、故人の霊を否定するものではなく、むしろ故人への敬意を表し、新たな一歩を踏み出すための心の支えとなるものです。
清めの塩の使い方
葬儀の後、清めの塩を受け取った場合は、家の玄関前で体に振りかけるようにしましょう。ここでは、一般的な清めの塩の使い方を紹介します。
- 一軒家ならば門に入る前、集合住宅なら玄関に入る前に行うとよいでしょう。
- 清めの塩は胸、背中、足元の順番で振りかけ、手で軽く払いましょう。
- 1人の場合は自身で振りかけますが、家族がいる場合は手伝ってもらっても問題ありません。
ちなみに、近年では足元のみに塩をかけるというやり方をする方も増えています。
宗派による清めの塩に対する考えの違い
清めの塩に対する考え方は、宗派によって異なります。死を新たな旅立ちと捉える仏教では、死を穢れと捉えないため、清めの塩が使われない葬儀もあります。特に浄土真宗は、死を不浄なものとする考え方に対して否定的です。
一方で、古くから受け継がれてきた日本の伝統として、清めの塩の使用を容認している宗派もあります。神道と仏教の教えが融合した日本では、仏式の葬儀であっても清めの塩が用意されることがあります。大切なのは、それぞれの宗派の考えや個人の想いを尊重することです。清めの塩を使うかどうかは、個々の判断に委ねられています。葬儀後に塩を渡されたからといって、必ずしも使う必要はありません。
逆に、塩を渡されなかったけれど清めの塩を使いたい場合は、玄関先に自分で用意した塩を撒いてから家に入るとよいでしょう。
「一姫二太郎」とはどういうことか


育児や子育てに関して、よく「一姫二太郎」という言い方が使われます。しかし、その正しい意味を理解できているでしょうか。
「一姫二太郎」の意味とは
古くから伝承される「一姫二太郎」という言葉は、家庭に最初に女の子、次に男の子が誕生することを指す言葉として親しまれています。これは、理想的な子どもたちの性別と生まれ順を表すものとして、多くの人々に受け継がれてきました。
「一姫二太郎」が意味するのは、子どもの人数ではなく、男女の組み合わせです。つまり、最初の子どもが女の子で、次の子どもが男の子であれば、たとえその後何人子どもが生まれても、この言葉が当てはまります。この言葉が示すのは、男女のバランスが整った家庭は幸福に満ち溢れるという考え方です。
女の子は優しさと思いやりに溢れ、男の子は頼りがいがあり勇敢というイメージが根強くあり、そのような子どもたちが揃うことで、家庭はより温かく活気に満ちた場所になると信じられてきました。もちろん、現代社会においては、男女の役割分担はますます変化しており、「一姫二太郎」という考え方にとらわれる必要はありません。
しかし、古くから受け継がれてきたこの言葉には、子どもたちの成長を願う親の愛情や、幸せな家庭への憧憬が込められていると言えるでしょう。
「女の子1人に男の子2人が理想的」は間違った使い方
ある調査によると、3割以上の人が「一姫二太郎」という言葉の意味を誤解していることが明らかになりました。その誤解とは、「子どもは女の子1人、男の子2人が理想的」というものです。誤解が多い年代は10代後半から20代前半と50代。特に50代は約4割の人が誤解しており、他の年代よりも高い割合となっています。
この誤解の理由はいくつか考えられます。まず、「太郎」は男の子の名前として広く知られているため、「二太郎」を男の子の人数と捉えてしまうという説があります。また、「一姫二太郎」という数字の並びから、「女の子1人、男の子2人」という組み合わせを連想してしまうという説もあります。
しかし本来、「太郎」は男の子を指すのではなく、「長男」を意味する言葉です。つまり、「一姫二太郎」は「最初の子どもが長女、次の子どもが長男であるのが理想的」という考え方を表しているのです。
「一姫二太郎」のメリット
「一姫二太郎」は、ただの言い伝えではなく、実際の子育てにも利点があると考えられています。一般的に、女の子はおとなしい性格で、育てやすいとされています。対照的に、男の子はやんちゃのことが多く、育児に労力を使う場合が多いとされています。
最初に女の子を育てた経験があると、2人目が男の子であっても冷静に対処できます。さらに、女の子は幼い頃からしっかりしており、弟の世話にも積極的であるため、母親の育児負担を軽減できるとも言われています。
「一姫二太郎」のデメリット
確かに「一姫二太郎」には様々なメリットがあるでしょう。しかし、デメリットも存在します。例えば、1人目の理想とは異なる子育てを強いられる場合や、男女の育児におけるギャップを感じることがあるかもしれません。
そもそも子育てのしやすさは性別によって決まるものではありません。子どもの個性は性別とは関係なく、親の反応や環境など様々な要素によって形成されるものだからです。
「一姫二太郎」という言葉には、昔からの性別をもとにした先入観が根強く残っています。昔は「女の子だから」、「男の子だから」といった性別による決めつけが当たり前でした。しかし、そのような考え方には何の根拠もなく、現代では単に性差別を助長するだけとなっています。今後、「一姫二太郎」という言葉は使われなくなっていくかもしれません。
性別にとらわれず、個性を尊重する社会が実現すれば、子どもたちはより自由に、伸び伸びと成長できるでしょう。
「一姫二太郎」は果たして理想的か
「一姫二太郎」の言い伝えによれば、子どもは1人目が女の子、2人目は男の子であれば育児しやすいということになります。しかしながら、男女の役割分担が変化している現代社会において、必ずしも「一姫二太郎」にこだわる必要はありません。子育てについての信念や理想は親や家庭ごとに違うのが当たり前です。
「一姫二太郎」の教えは参考にとどめ、生まれてきた子供を心から愛する姿勢が最も大切です。
霊柩車を見たら親指を隠す?


子供の頃に「霊柩車を見かけたら、親指を握って隠しなさい」と言われた経験のある方も多いでしょう。ここでは、霊柩車と親指の関係について考えます。
なぜ「霊柩車を見たら親指を隠せ」と言われているのか?
霊柩車を目にした時、親指を隠す必要性について明確な理由は未だ解明されておらず、様々な解釈が語り継がれています。 以下、特に広く知られている3つの説についてご紹介します。
親の死に目に会えないから
霊柩車を目にした際、親指を覆い隠す行為は、古くから伝承される慣習の1つです。その根底には様々な解釈がありますが、中でも広く知られているのが「親の死に目に会えない」という説です。
親は子よりも先に齢を重ねるため、多くは子が親を看取る形となります。しかし「親の死に目に会えない」という言葉には、単に親の最期に立ち会えないという意味だけでなく、子が親よりも先に死んでしまうという意味合いが込められています。言い伝えでは、霊柩車を見かけたときに親指を隠さないと、自ら親よりも先に命を絶ってしまうという不吉な運命を招くと信じられていました。これは子にとっても不幸な出来事ですが、何よりも親にとっては悲嘆に暮れる出来事となります。
故に、親は幼い子を不幸から守り、長寿を願って、霊柩車を見かけたら親指を隠すように諭していたと考えられます。それは親子の深い愛情と、子を思う切なる願いが込められた伝統的な行為と言えるでしょう。
親が早死にしてしまうから
霊柩車を目にする度に、「親の早死に」を懸念する地域が存在します。これは前述の「親の死に目に会えない」説と共通し、「親」という存在と密接な関係を持つ伝承です。「親指」が文字通り「両親」を連想させることから生まれたと考えられるこの説は、いずれにしても親への敬愛の念が根底にあると言えるでしょう。
縁起が悪いから
霊柩車を目にした際に親指を覆い隠す行為は、単なる縁起担ぎという解釈も存在します。古くからの伝承では、親指は魂の出入り口となる神聖な部位であり、それ故に不吉なイメージを持つ葬儀に遭遇した際には、その部位を覆い隠すことで悪霊の侵入を防ぐと信じられていました。
同様の伝承としては、「親指を握ると疫病から身を守ることができる」「夜道で親指を隠すと狐に化かされない」などがあり、いずれも親指が持つ神秘的なイメージに由来する迷信と言えます。
霊柩車を見たときに親指を隠す意味とその理由
そもそも、「親指を覆い隠す」という行為には、どのような意味や起源が存在するのでしょうか。ここでは親指にまつわる2つの伝承を基に、その行為に込められた想いと、その背景にある由来を深く掘り下げて考察していくことにします。
親指は魂が出入りする部位
前述の通り、古来より親指は魂の出入口として捉えられており、他者の魂魄が親指を通じて身体に侵入するという迷信が存在しました。葬儀においては、故人の霊魂や彷徨える浮遊霊が周囲を漂い、生者の肉体に取り憑こうとすると考えられていたため、葬儀を象徴する霊柩車を見かけると、親指から死者の霊が侵入するのを防ぐために親指を隠すようになったという説もあります。
実際、霊柩車が誕生する以前から、死者を火葬する儀式である「野辺送り」の際には、親指を隠すことが習慣化されていたという記録が残されています。
親指を隠すのは敬意の表現
仏教の礼法には「合掌」と呼ばれる所作があります。これは、両手を胸の前で合わせ、指先を合わせることで敬意を表すものです。合掌の際に親指を内側に入れるのは、仏教の教えである「六根清浄」を象徴しています。六根とは、眼・耳・鼻・舌・身・意の6つの感覚器官であり、親指を内側に入れることで、これらの感覚器官を制御し、心を清めることを意味しています。
霊柩車を見ると親指を隠すという習慣は、この合掌の所作から派生したと考えられます。霊柩車は死者を運ぶ車であり、死は不浄なものと捉えられていました。そのため、死穢(しえ)に触れないように、親指を内側に入れて合掌をする代わりに、親指を隠すようになったという説があるのです。また親指は生命の象徴と捉えられていたため、霊柩車を見ることで生命力が弱ってしまうとも考えられていました。したがって、親指を隠すことで、生命力を守ろうとしたという説もあります。
このように、霊柩車を見ると親指を隠すという習慣には、様々な意味や由来があります。いずれにしても、死そのものや亡くなった方に対しての敬意を表し、自分自身を守るための行為であると考えられています。



「霊柩車を見たら親指を隠す」という言い伝えには、死者への敬意や、
自分自身を守るための知恵が込められていると言えそうですね。



近年では霊柩車を見る機会も減ってきました。しかし、先人の知恵や文化を知ることは、現代社会を生きる私たちにとっても大切な学びの場となるでしょう。