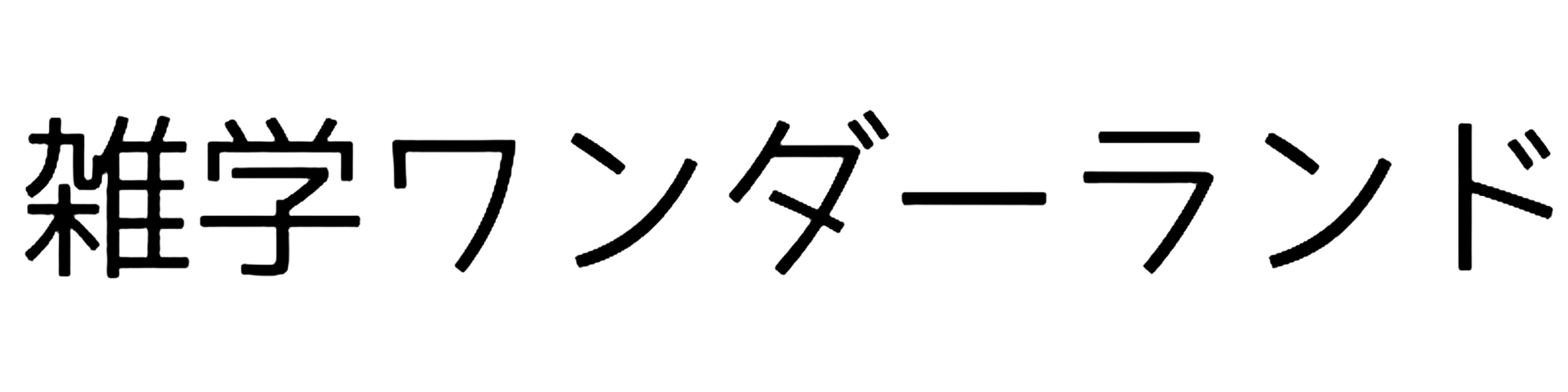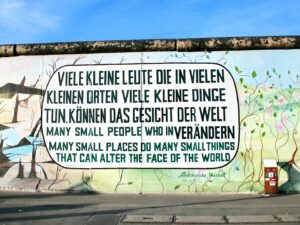チエコさん
チエコさん室町時代、くじ引きの結果将軍に選ばれた人がいるそうですね。



室町幕府の第6代征夷大将軍の足利義教です。詳しく見ていきましょう。
足利義教とは
「紙本著色足利義教像」引用:Wikipedia
足利義教は、室町幕府の第6代将軍です。第3代将軍・足利義満の子として生まれ、10歳で出家して義円(ぎえん)と名乗りました。25歳のときに天台座主に就任し、権力を蓄積しました。
義教は、政治基盤の弱い室町幕府の権威を強化するため、以下の3つの政策を推進しました。
- 将軍権力の強化
- 幕府直轄領の拡大
- 地方の統制強化
義教は、将軍の地位を世襲制にすることで、将軍権力の安定化を図り、また幕府直轄領を拡大することで、幕府の財政基盤を強化しました。さらに、地方の統制強化のために、奉公衆や奉行衆などの制度を整備しました。
義教のこれらの政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げました。しかし、義教の強権的な政治手法は、多くの反発を招きました。特に、義教の息子である義政が将軍になると、義政と義教の側近たちとの間で対立が深まり、義教は暗殺されることになりました。
義教は、室町幕府の政治体制の確立に大きな役割を果たした人物です。しかし、その独善的な政治手法は、室町幕府の政治的混乱を招いた一因にもなりました。
以下に、足利義教の人物像をまとめます。
- 強靭な意志と権力欲を持った人物
- 室町幕府の権威強化に尽力した人物
- 強権的な政治手法で多くの反発を招いた人物
足利義教は、室町幕府の歴史において、極めて重要な役割を果たしたと言ってよいでしょう。その人物像は、現在でも多くの議論の対象となっています。
足利義教の生涯
「足利義教像(法観寺蔵)還俗間もない頃の姿と伝わる」引用:Wikipedia
足利義教が将軍に就任するまでの経緯は、以下のとおりです。
将軍に就任するまで
足利義教は、第3代将軍・足利義満の子として生まれました。しかし、義満の正室・日野康子との間に生まれた子ではなかったため、将軍継承の可能性は低いものでした。
先にも書いた通り、10歳のときに出家して義円と名乗り、天台座主に就任しました。義教は、出家することで世俗的な権力欲を抑え、天台宗の権威を背景に権力を蓄積していきました。
1428年、兄の足利義持が急病で亡くなりましたが、義持には嫡子がいなかったため、後継者の選定が急務となりました。幕府内での候補者は、義円と、義持の猶子であった足利持氏の2人でしたが、その持氏は、義教と対立する細川勝元ら守護大名の支持を受けていました。ここで義円は、くじ引きで後継者を決める方式を提案し、その結果、義円が選ばれました。
しかし義円は元服前に出家していたため無位無官であり、出家者が還俗(げんぞく)して幕府に戻った先例もありませんでした。そのため幕府関係者の大半が義円の髪が伸びて元服が行えるようになってから将軍に昇進させるべきと考え、公卿の大半も同じ意見でした。幕閣はこれらの意見を尊重し、義円の髪が生えるまで待ち、義円は1429年に征夷大将軍に就任、名前も「義教」へと改めました。
義教の将軍就任は、幕府内での権力闘争の勝利でもありました。義教は、将軍として強引な政治手法で幕府の権威強化に努め、室町幕府の政治体制の確立に大きな役割を果たしました。
くじ引きで将軍に就任した背景
足利義教がくじ引きで将軍に就任した背景には、当時の室町幕府の政治情勢が大きく関係しています。
当時の室町幕府は、第3代将軍・足利義満の死後、将軍の権威が低下し、守護大名や有力寺社などの勢力が台頭していました。そのため、後継者の選定をめぐって、幕府内での権力闘争が激化していました。
義教は、兄の足利義持の猶子であった足利持氏と後継者を争っていました。持氏は、義持の正室・日野康子との間に生まれた子であり、義教と比べて将軍継承の可能性が高いとされていました。
しかし、義教は、持氏が義持の側近である細川勝元ら守護大名の支持を受けていたことを危惧していました。そこで、義教はくじ引きで後継者を決める方式を提案しました。くじ引きは、神意に委ねるという意味合いがあり、当時の社会では、決断の際によく用いられる方法でした。義教は、くじ引きによって、持氏が持っていた守護大名の支持を分断し、自分を有利な立場にしようと考えていたと考えられます。
1428年、義持が急病で亡くなった後、幕府の重臣たちは、義教の提案を受け入れ、くじ引きで後継者を決めることになりました。そしてくじ引きの結果、義教が選ばれ、将軍に就任しました。義教は、持氏の反発を抑えるために、すぐに持氏を九州に追放しました。
なお、くじ引きの具体的な方法については、諸説あります。一説には、石清水八幡宮から2本の籤(くじ)が送られてきて、そのうちの1本を引いた者が将軍に選ばれたと言われています。もう一つの説によると、義教と持氏がそれぞれ籤を引いて、その結果を比較したと言われています。
いずれにしても、くじ引きによって後継者が決まったことは、当時の室町幕府の政治情勢を示すものであり、足利義教の将軍就任は、室町幕府の歴史に大きな転換点となりました。
足利義教の政策
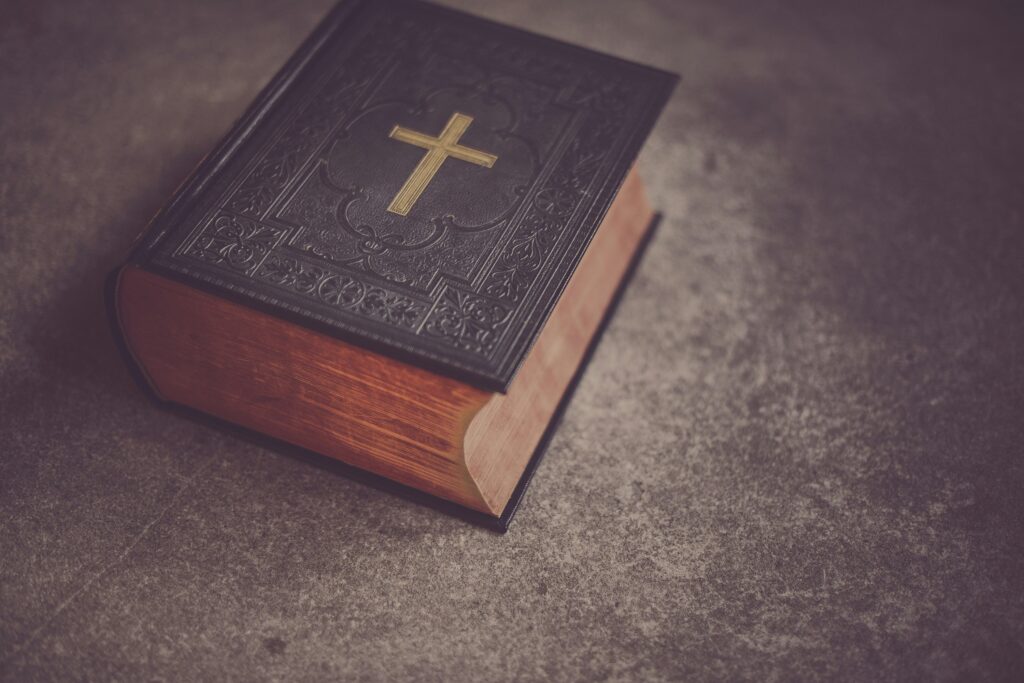
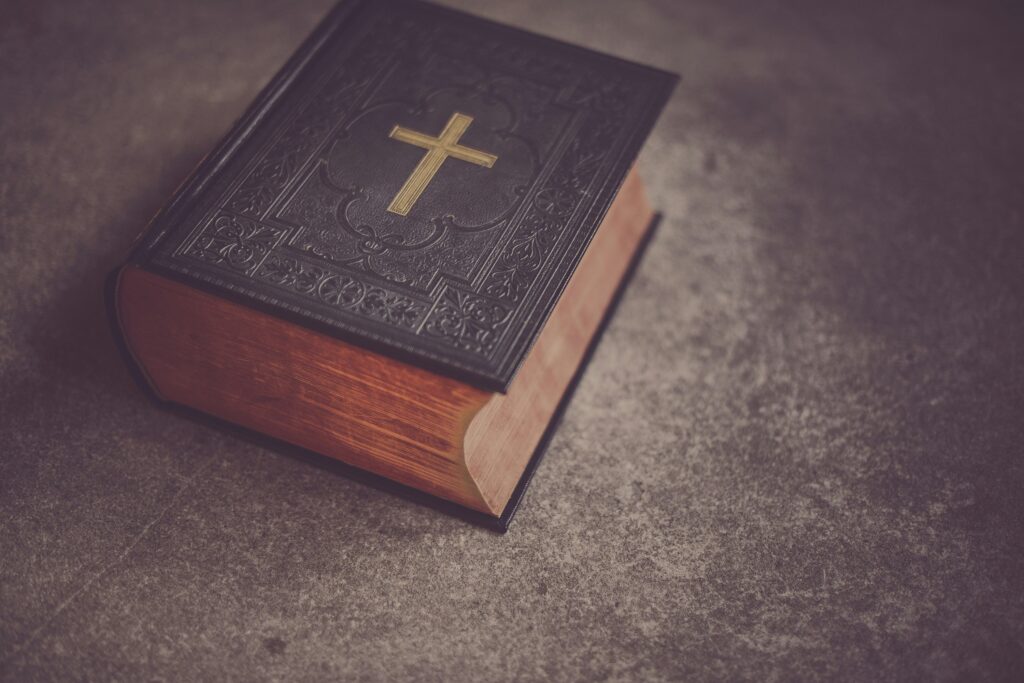
足利義教は将軍就任後、主に以下の3つの政策を推進しました。
政治政策
ここでは足利義教の政策上の特徴を説明します。
将軍権力の強化
義教は、将軍の地位を世襲制にすることで、将軍権力の安定化を図りました。また、将軍の権限を拡大し、幕府の行政を直接統括する権限を与えました。
幕府直轄領の拡大
義教は、幕府直轄領を拡大することで、幕府の財政基盤を強化しました。そのために、守護大名の所領を没収したり、新田開発を進めたりして、幕府直轄領を拡大しました。
地方の統制強化
義教は、地方の統制強化のために、奉公衆や奉行衆などの制度を整備しました。奉公衆は、幕府の直臣として、地方の守護大名の監視や統制を担い、さらに、地方の行政を担当する官僚として、幕府の権威を地方に浸透させる役割を果たしました。
強権的な政治手法
これらの政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げました。しかし、義教の強権的な政治手法は、多くの反発を招きました。特に、義教の息子である義政が将軍になると、義政と義教の側近たちとの間で対立が深まり、後に義教は享年48で暗殺されました。
義教は、室町幕府の政治体制の確立に大きな役割を果たした人物です。しかし、その政治手法は室町幕府の政治的混乱を招く一因ともなったと言えるでしょう。
宗教政策
足利義教は、将軍就任後に、以下の宗教政策を採りました。
寺社勢力の抑制
義教は、寺社勢力の拡大を抑制するために、以下の政策を実施しました。
- 寺社の所領を没収
- 寺社領の一部を幕府直轄地に編入
- 寺社領の無断使用を禁止
これらの政策により、寺社勢力の経済基盤は弱体化し、幕府の権威は強化されました。
仏教の統制
義教は、仏教の統制を強化するために、以下の政策を実施しました。
- 南北朝時代に争った南禅寺と建仁寺を合寺
- 天台宗の勢力を抑制
- 禅宗の勢力を拡大
これらの政策により、仏教の統一が進み、幕府の宗教政策への従順性が高まりました。
キリスト教の布教禁止
義教は、キリスト教の布教を禁止しました。これは、キリスト教が西洋の勢力と結びついて、幕府の権威を脅かすのではないかと危惧したためと考えられます。
具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。
義教は、南禅寺と建仁寺を合寺し、南禅寺を幕府の保護下におきました。
義教は、天台宗の勢力を抑制するために、天台座主の選出権を幕府に掌握しました。
義教は、キリスト教の布教を禁止する布教禁止令を発しました。
義教の宗教政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げました。しかし、寺社勢力や仏教界からの反発を招き、
また、キリスト教の布教禁止は、幕府の国際的地位を低下させる結果となりました。
訴訟政策
足利義教は、訴訟の政策にも力を入れました。訴訟制度を整えることで訴訟の利用を促進するとともに、幕府の訴訟権限を強化する目的がありました。
御前沙汰の強化
義教は、御前沙汰を強化することで、幕府の訴訟権限を拡大しました。御前沙汰とは、将軍が直接裁判を行う制度です。義教は、御前沙汰の審理を迅速かつ公正に行うために、裁判官の任命や訴訟手続きの整備を進めました。
奉行衆の設置
義教は、奉行衆を設置することで、地方の訴訟を迅速かつ公正に処理できるようにしました。奉行衆とは、幕府の直臣として、地方の行政を担当する官僚です。義教は、奉行衆に訴訟の担当権限を与え、地方の訴訟の処理を迅速化しました。
訴訟の簡素化
義教は、訴訟の手続きを簡素化することで、訴訟の費用を抑制し、訴訟の利用を促進しました。
また、訴訟の期間を短縮したり、訴訟の費用を減額したりするなどの改革を行いました。
義教の訴訟政策は、室町幕府の訴訟制度の整備に大きな役割を果たしました。
御前沙汰の強化や奉行衆の設置により、幕府の訴訟権限が拡大し、訴訟の迅速化や公正化が進みました。
また、訴訟の簡素化により、訴訟の費用が抑制され、訴訟の利用が促進されました。
足利義教への評価
「足利義教木像(等持院)」引用:Wikipedia
足利義教に対してはは、政策とその人物像に対して以下のような評価がなされています。
政策の成果
義教の一連の政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げました。将軍権力の強化、幕府直轄領の拡大、地方の統制強化などの政策により幕府の権威は強化され、中央集権化が進みました。また、訴訟制度の整備により、幕府の司法権が強化されました。
政策の方法
一方で、義教の政策は、強権的な方法で推進されたため、多くの反発を招きました。特に、寺社勢力や守護大名の反発は強く、義教の死後、応仁の乱などの混乱に発展しました。
人物としての評価
義教は、強靭な意志と権力欲を持った人物として評価されています。また、室町幕府の政治体制の確立に尽力した人物としても評価されています。一方で、強権的な政治手法で多くの反発を招いた人物という評価もなされています。足利義教は、室町幕府の歴史において、重要な役割を果たした人物です。その人物像は、現在でも多くの議論の対象となっています。
まとめ


足利義教は、1394年に第3代将軍・足利義満の四男として生まれ、幼名は春寅でした。10歳のときに出家して義円と名乗り、天台座主に就任しました。
1428年、兄の足利義持が急病で亡くなった後、義教はくじ引きで室町幕府の第6代将軍に選ばれました。義教は、将軍として強権的な政治手法で幕府の権威強化に努め、室町幕府の政治体制の確立に大きな役割を果たしました。
義教の政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げました。将軍権力の強化、幕府直轄領の拡大、地方の統制強化などの政策により、幕府の権威は強化され、中央集権化が進みました。また、訴訟制度の整備により、幕府の司法権が強化されました。その一方、義教の政策は、強権的な方法で推進されたため、多くの反発を招きました。特に、寺社勢力や守護大名の反発は強く、義教の死後、応仁の乱などの混乱に発展しました。
足利義教は、室町幕府の歴史において、重要な役割を果たした人物です。その人物像は、現在でも多くの議論の対象となっています。義教の「くじ引き」での将軍就任は、当時の室町幕府の政治情勢を示すものであり、義教の将軍就任は、室町幕府の歴史に大きな転換点となりました。また、義教の一連の政策は、室町幕府の権威強化に一定の成果を上げましたが、強権的な方法で推進されたため、多くの反発を招き、義教の死後、応仁の乱などの混乱に発展しました。



ある意味、日本の国王と言ってもいい将軍が「くじ引き」で選ばれていたのは驚きですね。



室町幕府の統率者として一定の評価は得ていますが、その強権的な政治手法が影を落としています。